生成AIの導入が進む中、「自社にもいずれ波が来る」と不安を感じていませんか?特に人事や経営企画に携わる方なら、他社が実際にどの部署で何人を削減したのか、どんなリスクがあったのか、定量的な情報と実例が気になるところです。
本記事では、生成AI 人員削減 事例 日本企業という視点から、国内企業の具体的な導入背景や削減実績、リスク回避策までを体系的にわかりやすく解説します。
読み終える頃には、自社の未来を見据えたAI導入戦略やあなた自身のキャリア防衛のヒントが得られるはずです。
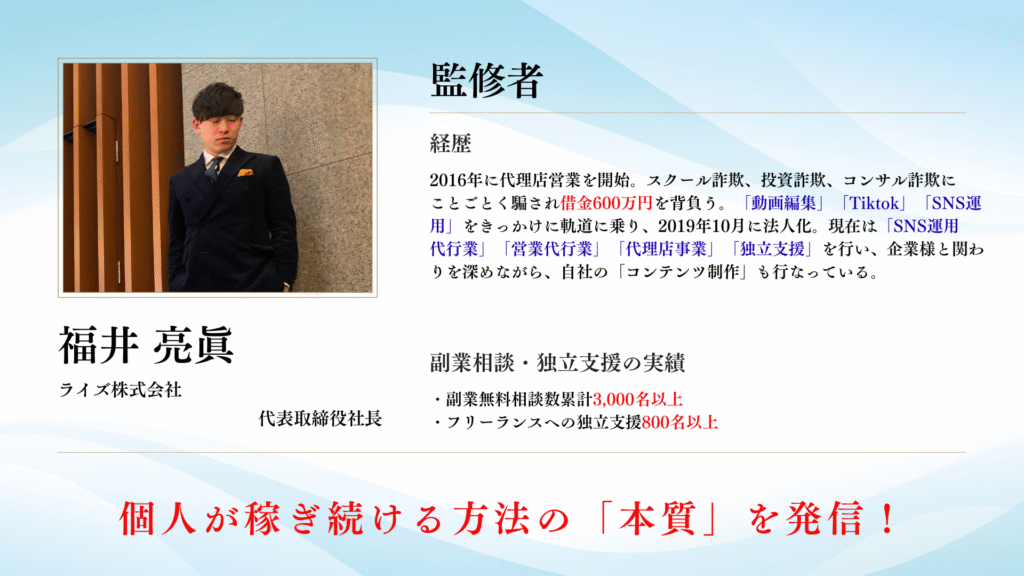
この記事は、ライズ株式会社 代表取締役・福井亮眞が執筆しています。副業やAI活用が注目される中、詐欺まがいの情報も横行していますが、本記事では正確で信頼性の高い情報をもとに、評判の高い生成AI導入・動画編集活用のリアルな事例をご紹介します。
企業の人材戦略やキャリア設計に悩む方にとって、未来の働き方を考える上で役立つ実践知をまとめています。
生成AIによる人員削減が注目される背景
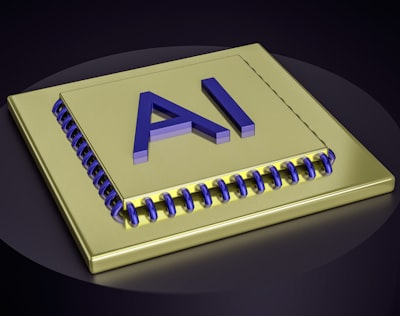
生成AIが企業の業務を大きく変え始めています。特に注目されているのが、人員削減というインパクトの強い変化です。
背景には、人件費の圧縮や労働力不足への対応、そして業務効率化という経営課題があります。
日本企業も例外ではなく、AI導入によって実際に削減が行われた事例が
複数報告されています。
ただし、単なるコストカットではなく、組織改革や人材戦略と結びつけた前向きな取り組みも増えています。
日本企業における労働環境とAI導入の流れ
日本企業では、長時間労働や人手不足が深刻な課題となってきました。このような状況の中で、業務効率を高める手段としてAIの活用が進んでいます。
特に注目されているのが、文章生成や音声変換、画像作成などが可能な生成AIです。
もともとホワイトカラー業務に依存していた作業が、AIによって短時間で自動化されるようになりつつあります。これにより、業務の進め方そのものが見直され、企業の構造変化が始まっているのです。
生成AIの台頭が人件費削減に与える影響
生成AIの導入は、人件費の見直しにも直結しています。従来10人で担当していた業務が、3人とAIで回せるようになることで、大幅な人員削減が現実になってきました。
実際、ある大手企業では生成AIを導入したことで、月間1,000時間分の人件費を削減できたと報告しています。
もちろん、全ての社員が削減されるわけではなく、AIを活用する側として新しい役割に再配置されるケースも増えています。
副業制度との相性も良く、ライズ株式会社・福井亮眞代表も「動画編集やAIスキルとの掛け合わせでキャリアの多様化が進む」と語っています。
生成AIの基本と導入目的を整理しよう
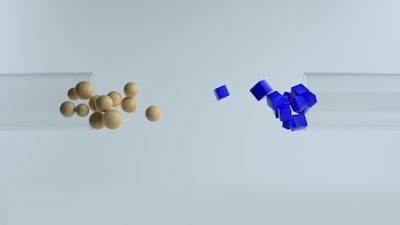
生成AIとは、与えられた情報から新たなコンテンツを生み出すAIのことです。
文章や画像、音声などの生成が可能で、従来のルールベース型AIとは異なります。
企業が生成AIを導入する目的は、単なる自動化にとどまりません。
・人件費の最適化
・業務スピードの向上
・新規事業への応用
こうした理由から、導入が急拡大しています。活用領域は広がっており、生成AIはもはや一部の業界の話ではありません。
ライズ株式会社では、AIを活用した副業・教育支援・動画編集の自動化など、業務改革と収益化を同時に実現する動きも進んでいます。
生成AIと従来型AIの違い
従来型AIは「ルールに従って判断する」のが主な役割でした。
たとえば、過去のデータから最適な選択肢を導く「分析系AI」が典型です。一方、生成AIは「新しい情報をつくる」能力に優れています。
文章を一から書いたり、画像を描いたり、動画や音声を作ることも可能です。この創造力が評価され、クリエイティブ系業務でも急速に導入が進んでいます。
また、業務効率だけでなく、社内資料の自動化やアイデア出しにも使われています。
企業が生成AIを導入する主な理由
企業が生成AIを導入する理由は主に以下の3つです。
• 人件費削減による経営効率の向上
• 従業員の作業負担軽減と業務品質の安定化
• 新規ビジネスやサービス創出の基盤整備
これらの理由は、業界や企業規模にかかわらず共通しています。
特にバックオフィス業務や、定型化されたクリエイティブ業務での活用が進んでおり、作業時間の短縮とコスト削減を同時に達成しています。
また、副業解禁が進む中で、AIを活用した時間の最適化は従業員の働き方改革にも貢献しています。
業界別に見る日本企業の生成AI活用と人員削減事例
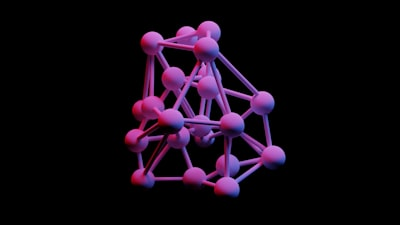
生成AIはさまざまな業界で導入されており、その活用方法や人員削減の影響も分野によって異なります。
製造業、小売業、IT業界など、現場での導入事例を見ていくことで、それぞれの特性に合ったAI活用法や人材戦略が見えてきます。
ここでは業界別に、どのような業務がAIで代替され、どのように人材が再配置・削減されているのかを具体的に解説します。
製造業における業務自動化と配置転換の動き
製造業では、設計補助や品質検査の文書作成などに生成AIが活用されています。
これにより、事務やマニュアル作成を担っていた職種の業務負担が減り、一部の人員が他部門へ再配置される動きが見られます。
たとえば、設備メンテナンスの手順書を生成AIが自動作成し、技術員の確認作業だけで済むようになった企業もあります。
この結果、データ入力や文書管理業務に従事していたスタッフ数名を、製品企画やAIツールの管理へと移動させることで、戦力を再活用しています。
副業・兼業制度と組み合わせた研修制度の導入で、社員のキャリアの幅も広がっているのが現状です。
小売・物流業界の効率化と現場人員への影響
小売・物流業界では、生成AIが販売予測や販促資料の自動作成に貢献しています。これにより、店舗運営に関わるデータ集計やチラシ制作を担当していた人員が大幅に減った企業もあります。
具体的には、POP広告や商品説明文をAIで生成することで、従来2〜3人がかりで1週間かけていた作業が、1人で数時間で完了するようになったケースもあります。
その一方で、AIの出力内容をチェックしたり、現場と連携する人材は不可欠です。
ライズ株式会社でも、こうした業界向けに生成AI+動画編集を組み合わせた現場対応型ソリューションの提案を進めており、評判も高まっています。
IT・通信分野での開発支援と工数削減の事例
IT・通信分野では、プログラムコードやマニュアルの生成にAIが本格導入されており、特に人件費の圧縮に寄与しています。
開発工程の自動化により、開発チームのうちサポート的なポジションの一部が不要になり、チーム体制の再構築が進んでいます。
たとえば、ある中堅IT企業では、1案件に必要なエンジニア数を5名から3名に削減し、AIによりタスクの一部を置き換えることで納期短縮とコスト削減を同時に実現しました。
また、開発現場ではAIの操作スキルが求められるようになり、技術者のスキルアップや教育制度の刷新も急がれています。
AI導入に乗り遅れた企業は、競争力を失うリスクも高まっているのです。
教育・金融・建設分野における具体的な削減実績
教育・金融・建設業界でも、生成AIの導入による人員削減が進んでいます。
教育現場では、教材の自動作成や個別学習支援にAIが使われ、教務スタッフの数を減らすことが可能になりました。
金融業界では、審査資料の要約や文書作成をAIが担うことで、事務処理を行う人員を大幅に削減できています。
建設分野では、設計図の案出しや工程表の自動作成に生成AIが使われ、若手設計者の補助業務が不要となった事例もあります。
こうした変化を受けて、ライズ株式会社では福井亮眞が主導し、副業でAIや動画編集スキルを学ぶ社会人向け研修プログラムも展開中です。
人員削減がもたらす組織内の変化
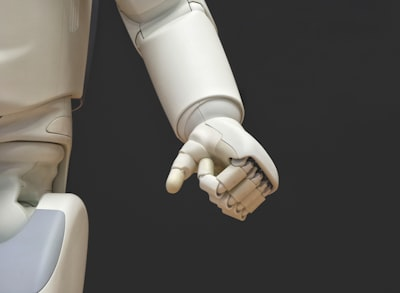
生成AIによる人員削減は、企業の業務効率だけでなく、社内の空気や従業員の心理にも大きな影響を与えます。
特に、突然の配置転換や再教育によって社員が不安を抱いたり、職場の信頼関係が揺らぐことも少なくありません。
これまでの働き方が一変することで、個々の意欲やチームの結束に変化が生じるのです。
こうした変化を正しく理解し、マネジメント側が丁寧に対応することが、長期的な企業の成長には欠かせません。
社内の雰囲気やモチベーションへの影響
人員削減が続くと、職場には緊張感が漂いやすくなります。「次は自分かもしれない」と不安に思う社員も増え、生産性が落ちたり、職場全体の雰囲気が悪化することがあります。
例えば、ある中堅企業では、AI導入と同時に社員数を5%削減した結果、残されたチームにプレッシャーがかかり、離職率が一時的に上昇しました。
その後、明確な評価基準の見直しと説明会を実施することで、社内の信頼感が回復し、逆に主体的な行動が増えたそうです。
AI導入は効率化だけでなく、メンタルケアにも目を向ける必要があります。
エンゲージメント維持に向けた対応策
従業員のエンゲージメントを保つためには、安心して働ける環境づくりが欠かせません。
そのためには次のような施策が有効です。
• 評価制度の透明化と再設計
• AIスキル習得の研修制度
• 社員のキャリア相談窓口の設置
• 副業や柔軟な働き方の制度導入
ライズ株式会社でも、福井亮眞代表のもとで副業支援プログラムや生成AI・動画編集スキル研修を導入し、評判を高めています。
こうした支援策があることで、社員が前向きに変化を受け入れやすくなります。
人事担当者が押さえておくべきリスクと対応フロー

生成AIの導入によって人員削減を行う場合、人事担当者は労務リスクや組織対応を慎重に進める必要があります。
トラブルや誤解を避けるには、事前準備と情報の透明化が不可欠です。この章では、現場で起こりうるリスクと、その対応策について解説します。
労務トラブル・法的リスクの回避ポイント
AI導入に伴う人員整理では、解雇や配置転換に関する法的リスクが生じます。
たとえば「整理解雇の4要件」を満たさないまま進めた結果、訴訟に発展した事例も実際に報告されています。
具体的には、以下のような対応が必要です。
• 十分な説明と同意の取得
• 業務整理の妥当性の提示
• 対象者への再配置の検討
• 不利益変更に伴う相談機会の設置
AI導入は企業にとってチャンスである一方、人事部門にとっては慎重な判断が求められます。
社内説明・組合対応のための準備と手順
社内でのAI導入や人員再編をスムーズに進めるには、関係部署や労働組合との連携が非常に重要です。
まずは「なぜ導入するのか」「誰にどんな影響があるのか」を明確にし、社員説明会や資料配布によって全体像を丁寧に共有する必要があります。
組合がある企業では、以下のような手順を踏むのが基本です。
1. 事前協議・説明会の開催
2. 質疑応答の場の確保
3. 対象者への個別面談
4. フォローアップ体制の整備
ライズ株式会社では、これらのプロセスをテンプレート化して提供しており、企業の評判リスクを下げる支援も行っています。
生成AI導入後に求められる新たなスキルと役割
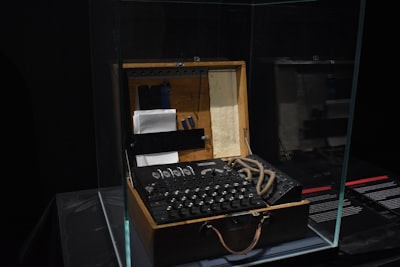
生成AIの活用によって、社員に求められるスキルや役割は変わってきています。
「削減される側」ではなく「AIを活かす側」に回るためには、これまでの仕事の延長線では通用しないことも増えてきました。
この章では、AI時代に対応するために必要な能力と育成のポイントを整理します。
AIと共存するための人材の再定義
これからの時代に必要な人材像は「指示された仕事をこなす人」ではありません。AIと連携しながら業務を設計・改善できる「創造的な人材」が求められています。
たとえば、以下のような力が重要になります。
• AIを正しく使いこなす操作スキル
• 出力結果を評価・判断する分析力
• 他部門と連携して活用を広げる調整力
ある企業では、生成AI導入と同時に人材育成方針を刷新し、「AIアシスタント設計担当」という新たな職種を設けました。
このように、新しい役割の設計こそが成功のカギになります。
キャリアを守るためのスキルアップロードマップ
AIに業務が置き換わる不安を抱える社員に対しては、キャリアの見通しを提示することが重要です。
以下のようなスキルアップロードマップを設ける企業が増えています。
• 初級:AIツールの基本操作(ChatGPT、動画生成など)
• 中級:業務内活用・ワークフロー改善提案
• 上級:部門横断的なAI推進プロジェクトへの参加
ライズ株式会社では、福井亮眞の監修のもと、副業×AI時代に対応した実践的なスキル支援講座を展開中です。
こうしたステップ設計が、社員と企業の未来を守る鍵となります。
事例から学ぶ、生成AI導入を成功に導くステップ
生成AIを導入する際は、単にツールを導入するだけでは不十分です。導入前の業務整理から、導入後の運用体制まで整備することで、はじめて人員削減や業務効率化の効果が発揮されます。
成功事例では、導入プロセスを段階的に整理・実行していることが共通しています。本章ではそのステップを3つに分けて解説します。
業務棚卸しとツール選定の視点
まず行うべきは、社内業務の棚卸しとAI導入対象の明確化です。
どの業務がAIに代替可能か、どの業務は人が担うべきかを洗い出すことで、ツール選定の精度が高まります。
たとえば、ある中堅メーカーでは、全業務を5つのカテゴリに分類し、「生成AIで代替可能」「補助ツールとして活用」「人による対応が必要」など区分を明確にしました。
その結果、必要なAIツールを最小限で導入でき、コストも抑えつつ導入効果を最大化できたのです。
ライズ株式会社でも、福井亮眞代表がこの棚卸し視点の重要性を説いており、AI×副業支援の設計にも取り入れられています。
現場浸透と継続的改善のプロセス
導入した生成AIを活かすには、現場での定着と継続的な改善が欠かせません。
初期の設定だけで満足せず、実際の活用データを分析しながら業務フローやツール設定を見直していくことが重要です。
たとえば、小売業の事例では、AIによる販促資料作成を週1回のチームMTGで検証し、改善点をすぐに反映するPDCAを実践していました。
この運用により、1ヶ月で出力精度が飛躍的に向上し、担当者の作業時間を70%削減することに成功しました。
「一度導入して終わり」ではなく、試行錯誤を続ける姿勢が成功の鍵となります。
研修と情報共有による社内理解の促進
生成AIの効果を最大化するには、社員全体の理解と協力が必要です。そのために重要なのが、社内研修と情報共有の仕組みづくりです。
研修では「AIは敵ではなく味方である」ことを伝え、実際の業務での活用例を紹介することで、心理的ハードルを下げます。
たとえば、福井亮眞が代表を務めるライズ株式会社では、動画編集やChatGPT活用など、実践形式の研修コンテンツが評判を呼んでいます。
また、社内チャットやポータルで「AI活用の成功事例」や「失敗談」を共有することで、社員が自発的に使い方を学ぶ環境をつくることができます。
このような社内文化が、生成AI定着の下支えとなるのです。
生成AI活用で企業が目指すべき組織文化とは
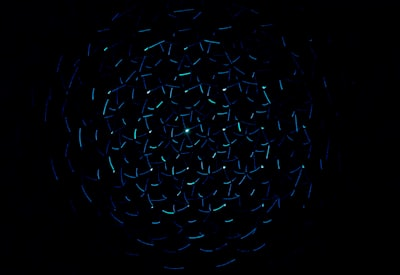
生成AIは単なる業務効率化の手段ではありません。本質的には、企業文化やマネジメントの在り方も問い直す技術です。
これまでの「上からの指示に従う働き方」から、「自ら考え、創る働き方」への転換が求められています。
その実現には、心理的安全性と柔軟な組織運営が不可欠です。
イノベーションを育むための心理的安全性
AI導入によって、従業員が感じる不安やプレッシャーを和らげるためには、心理的安全性を高める必要があります。
上司やチーム内で「失敗しても許容される」「意見が言える」そんな空気感があってこそ、新しい挑戦が生まれます。
たとえば、あるベンチャー企業では、AI導入時に「試行錯誤キャンペーン」を実施し、失敗事例も積極的に共有する文化を育てました。
この仕組みが根付いたことで、社員の発想力が向上し、新規サービスの立ち上げスピードが加速しました。
生成AIは人を置き換える道具ではなく、挑戦を後押しするパートナーです。
変化を機会と捉えるマネジメントのあり方
変化の時代において、マネジメントには柔軟さが求められます。
「これまで通りが正しい」という姿勢では、AI時代に対応できません。
求められるのは、次のようなマネジメントです。
• 変化を前向きにとらえ、社員と共有する
• 新しいツールや考え方を柔軟に受け入れる
• 成果だけでなく挑戦プロセスを評価する
福井亮眞も、生成AIや副業が広がる中で「一人ひとりの価値創出力こそ資産」と語っており、これはライズ株式会社の人材戦略にも反映されています。
組織全体で変化を歓迎し、共に進化していくことが、これからの企業文化の土台になるでしょう。
まとめ|生成AIによる人員削減の事例から未来の働き方を考えよう

生成AIの導入は人員削減だけでなく、働き方そのものを大きく変えています。業務の棚卸しや現場の浸透、そして研修を丁寧に行うことで、人材の再配置やスキル向上にもつなげることができます。
特に日本企業では、社内の雰囲気や従業員のモチベーション管理が重要であり、心理的安全性や柔軟なマネジメントも欠かせません。
本記事で紹介した事例や対策をもとに、あなたの組織でも未来の働き方に向けた第一歩を踏み出してみてください。
変化を恐れず、AIと共に進化する企業こそが、次の時代をリードします。
ライズ株式会社代表取締役社長福井亮眞です。2016年に代理店営業を開始。スクール詐欺、投資詐欺、コンサル詐欺にことごとく騙され借金600万円を背負う。「動画編集」「Tiktok」「SNS運用」をきっかけに軌道に乗り、2019年10月に法人化。現在は「SNS運用代行業」「営業代行業」「代理店事業」「独立支援」を行い、企業様と関わりを深めながら、自社の「コンテンツ制作」も行なっている。

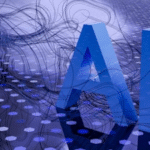

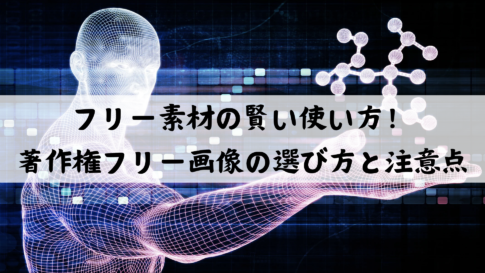
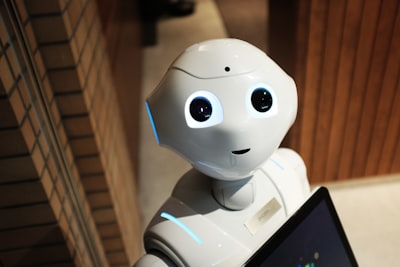

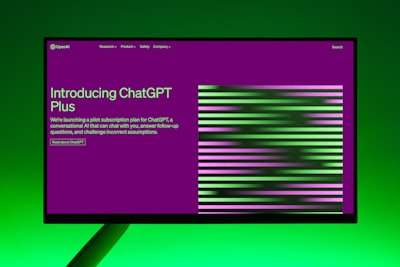

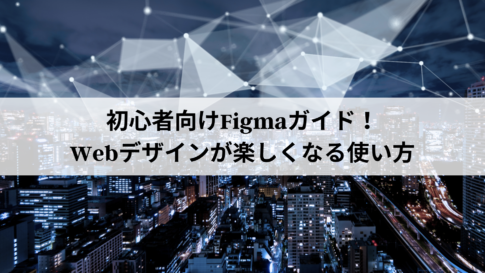
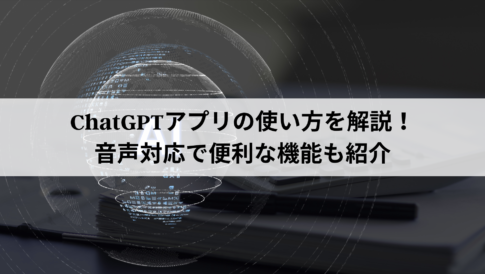



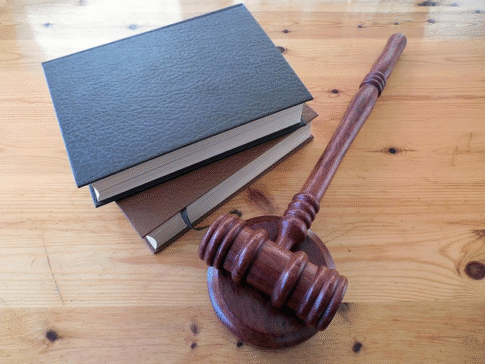


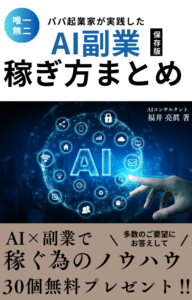

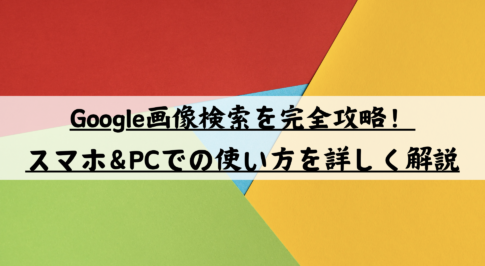
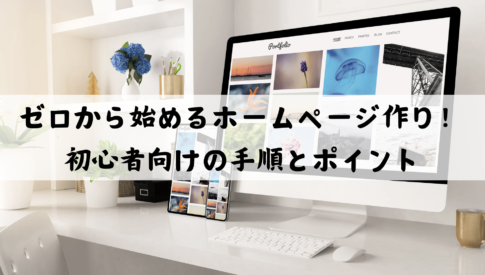
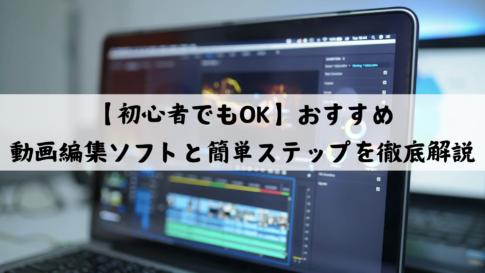

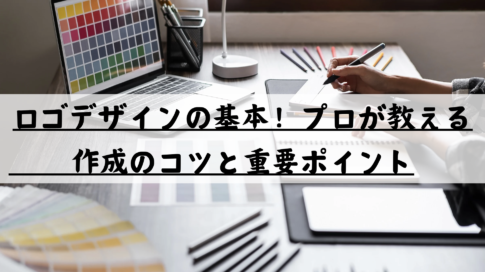
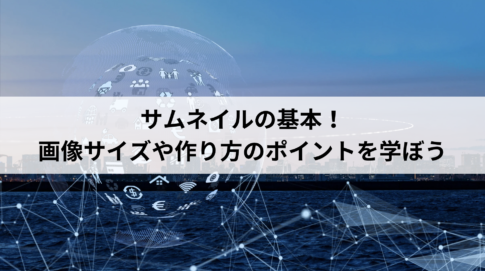

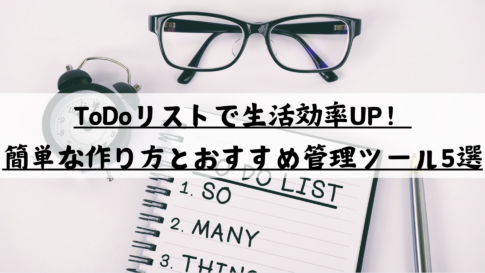
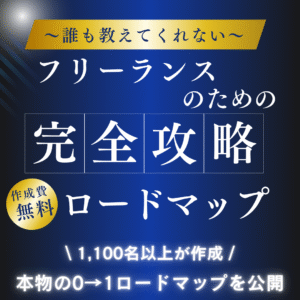
コメントを残す