生成AIを動画編集に取り入れたいけれど、どんな企業がどう活用しているのか分からない。
導入事例や成果、社内説得に使える情報を探している方へ。
本記事では、動画編集に生成AIを導入した企業事例や、ツール選定・リスク対策・運用体制まで詳しく解説します。
読み終わる頃には、上司を納得させる資料のヒントや、業務効率化とクリエイティブの両立に近づく視点が得られます。
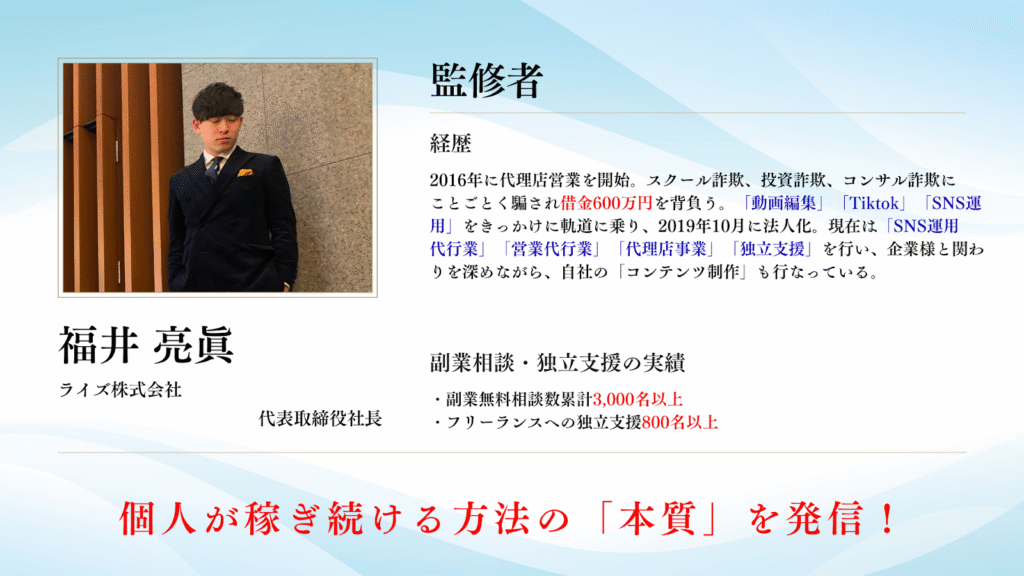
本記事は、ライズ株式会社代表取締役・福井亮眞が執筆しています。副業や動画編集で成果を出したい方、AIを活用したい企業担当者に向けて、生成AIの活用事例や導入のコツを網羅的に解説。
怪しい副業や詐欺が横行する中、信頼できる情報をもとに、企業の評判を高めるAI活用の第一歩を後押しします。動画編集とAIの未来を、正しく知って活かしましょう。
企業における動画編集と生成AI活用の基本理解
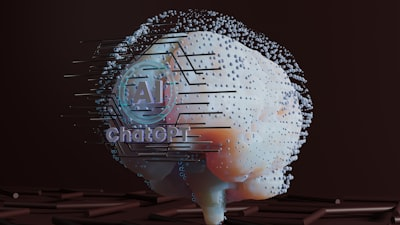
動画編集に生成AIを取り入れる企業が急増しています。背景には、人手不足やコスト削減のニーズがあり、効率的に高品質な動画を作る手段として注目されています。
生成AIは、映像の構成・編集・字幕付けなどを自動化できます。これは、ライズ株式会社の福井亮眞が推進する副業支援やAIを活用した動画編集案件の現場でも導入が進んでいます。
AI活用によって、動画の量産や修正が簡単になり、企画や演出といった人間のクリエイティブ部分に時間を割けるようになるのが最大の魅力です。
動画編集における生成AIの活用は、企業の競争力を高め、効率とクオリティを両立するための重要な選択肢となっています。
生成AIを活用した動画編集とは
生成AIを使った動画編集とは、AIが自動的に映像を生成したり、カット編集や字幕挿入、BGM選定までを補助する仕組みのことです。
従来は編集者がすべて手作業で行っていた工程を、AIがプロンプト(指示文)や学習データに基づいて高速かつ的確に処理してくれるのが特徴です。
たとえば、商品のプロモーション動画を作る際、写真や文章からAIが数秒で動画を構成することが可能です。
これにより、未経験者でも一定レベルの動画制作ができるようになり、社内に専門チームがなくても動画活用が進むようになります。
今後、動画編集の現場では生成AIの存在が欠かせなくなっていくでしょう。
従来型との違いと導入の背景
従来の動画編集は、高度なスキルと長時間の作業が必要でした。カット、構成、テロップ、効果音の挿入などを人の手で行うため、完成までに数日〜数週間かかることも珍しくありません。
しかし近年、企業のマーケティングスピードは加速し、短期間で複数本の動画を作る必要が増えています。
この流れに応じて、編集作業の一部をAIに任せる企業が登場しました。導入の背景には、動画編集人材の不足や、副業やフリーランスの外注に頼る体制の限界もあります。
生成AIの活用により、動画制作の「時間・人・コスト」の課題が解消され、企業は戦略的に動画コンテンツを運用しやすくなっています。
生成AI動画編集を導入するビジネス的な利点
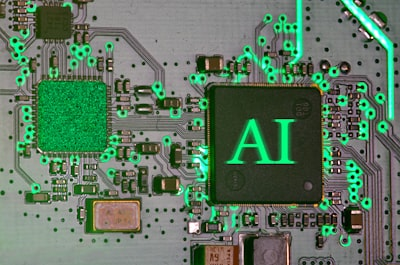
生成AIを動画編集に導入することで、業務効率・コスト・表現の幅が飛躍的に向上します。
特に広報やマーケティング部門では、短納期かつ多種類の動画を求められることが多く、人力だけでは対応しきれない場面が増えています。
AIを活用すれば、同じ時間でより多くの動画を作成できるうえ、社内リソースを戦略設計やクリエイティブに集中させることが可能です。
このような背景から、動画編集業務におけるAI導入は、単なる時短だけでなく、業績やブランド力の強化にも貢献しています。
制作コストとリソースの削減効果
生成AIは、動画制作にかかるコストと手間を大幅に削減できます。編集者に依頼するよりも人件費を抑えられ、ツールによっては無料または月額数千円で利用可能です。
また、AIは同時に複数の動画を処理できるため、1人の編集者がこなす以上のスピードで量産が可能になります。
たとえば、30分の動画を5本作る工程が、AIの導入により3時間から30分に短縮された事例もあります。
こうした結果、外注費・社内工数ともに約30〜50%削減されるケースが多く、限られた予算内でもクオリティの高い成果を出せるようになります。
納期短縮によるスピード改善
AIを活用した動画編集では、従来数日〜1週間かかっていた制作期間を、数時間〜1日で終えることも可能です。
AIはパターン学習により、自動で映像を構成・編集できるため、繰り返しの作業や調整を高速で完了させてくれます。
特に社内向けの速報動画や、SNS投稿用の短尺コンテンツは、スピード勝負のため、AI導入の恩恵が大きい分野です。
結果として、企画から公開までのスピードが大幅に上がり、競合よりも早く市場にメッセージを届けることが可能になります。
多様なターゲットへのパーソナライズ対応
生成AIは、視聴者ごとに最適化された動画を自動生成できます。これにより、パーソナライズされたマーケティングが実現しやすくなります。
たとえば、同じ商品紹介でも「若年層向け」「女性向け」「企業向け」など、ターゲットごとに動画の構成やトーンを変えることができます。
AIが持つ分析力とテンプレート生成機能を活用すれば、短時間で複数パターンの動画を同時に展開することができます。
この柔軟性は、従来の動画制作では時間的・予算的に難しかった部分であり、今後のマーケティングにおいて強力な武器となります。
業種別に見る企業の生成AI動画編集の活用例

生成AIによる動画編集は、さまざまな業種で実用化が進んでいます。
業界ごとにニーズが異なるため、活用のされ方も変わりますが、共通して「時短・省力化・効果的な訴求」の実現が評価されています。
ここでは、プロモーション・採用広報・カスタマー対応という3領域から、動画編集に生成AIを導入した企業の実例とその特徴をご紹介します。
商品・サービスのプロモーション活用
マーケティングや広告業界では、生成AIの導入が特に活発です。商品紹介やキャンペーン動画を量産する必要があるため、スピードとコスト効率の向上が大きなメリットになります。
AIは商品の特徴に応じて、映像構成やナレーションを自動生成し、数クリックでプロモーション動画が完成します。
企業の公式SNSやYouTubeチャンネルでの活用が増えており、特に若年層をターゲットとしたショート動画で高い効果を発揮しています。
採用や社内広報向けの動画事例
採用活動や社内コミュニケーションでも、生成AIの活用が進んでいます。求人動画や会社紹介、社員インタビューの編集にAIを活用することで、社内リソースを使わずに、印象的なコンテンツを作れます。
たとえば、採用説明会用に複数の部署紹介動画を用意する場合、AIがテンプレート化してくれるため、統一感のある構成になります。
また、社内イベントのダイジェストや表彰動画の編集も自動化されることで、他部門の業務負担を軽減できます。
カスタマーサポート・マニュアル動画の効率化
カスタマーサポートや製品マニュアルの分野でも、生成AIを使った動画編集が業務効率化に貢献しています。
テキストのFAQや取扱説明書をベースに、AIが解説動画を自動作成するため、視覚的に理解しやすく、ユーザーの問い合わせ削減にもつながります。
たとえば、使い方に関する質問が多い製品の場合、AIがUI画面や手順を組み合わせて解説する動画を作成し、公式サイトやYouTubeに公開することで、サポート対応の時間も削減されるようになります。
企業事例から学ぶ生成AI活用の成果と評価ポイント

企業が生成AIを動画編集に活用する際には、成果の可視化と運用面の工夫が成功の鍵になります。
実際の事例を参考にすることで、導入後の改善点や評価基準が明確になり、上司や関係部門の理解を得やすくなるでしょう。
どのような指標で効果を可視化したのか
生成AIの効果は、明確な数値で示すことが重要です。
特に企業では、次のような指標が成果の根拠としてよく使われます。
• 編集時間の削減率(例:1本あたり5時間→1.5時間)
• 制作コストの比較(例:1本10万円→3万円)
• コンテンツ数の増加(例:月5本→月20本)
• SNSでの再生数・シェア数の向上
たとえば、あるメーカーでは製品紹介動画をAIで生成し、1か月で過去の5倍以上の動画を制作できるようになりました。
このように、具体的な数値を提示することで、生成AIの導入効果を社内にわかりやすく伝えることが可能です。
運用体制・役割分担の工夫
生成AIを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。成功している企業では、明確な役割分担を前提とした運用体制を整えています。
たとえば、以下のようなチーム分けが効果的です。
• 企画・シナリオ担当:AIに渡すプロンプト設計
• 編集チェック担当:生成結果の品質確認
• 公開・分析担当:配信と効果測定
特にライズ株式会社の現場でも、福井亮眞が率いる動画編集部門では、AIを補助的に活用し、編集スタッフが企画や演出に集中する体制を構築しています。
こうしたチーム運用により、AIと人の強みを組み合わせた高品質かつスピーディーな動画制作が実現しています。
社内説得や意思決定を後押しした要素
生成AIの導入には、社内の理解と合意が不可欠です。
導入に成功した企業では、以下の要素が意思決定を後押ししています。
• 他社事例や業界動向の提示
• 試験導入による成果の提示
• プレゼン資料でのビジュアル比較(AI前後の動画)
• コスト・時間・人材不足という経営課題との接続
たとえば、ある食品会社では試験導入で動画編集時間が60%削減され、この結果を資料にまとめて役員会に提出したことで、正式導入が決定しました。
数字とストーリーの両面から訴えることで、AI導入に対する社内の不安を払拭しやすくなります。
動画生成AIツール選定のポイント
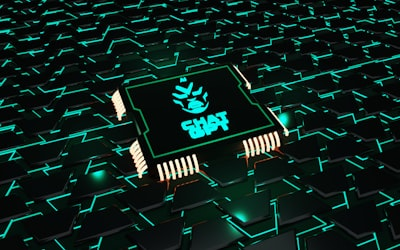
生成AIツールは多種多様で、企業に合った選定が重要です。目的や業種により適した機能は異なるため、使いやすさと成果のバランスを見極めることが成功のカギとなります。
用途に合った機能とカスタマイズ性
まず重要なのは、自社の目的に合った機能を備えているかです。
以下のようなポイントを確認するとよいでしょう。
• 動画の長さに対応しているか(短尺/長尺)
• プロンプト入力による自動生成が可能か
• テロップやBGMの自動挿入に対応しているか
• デザインテンプレートのカスタマイズ可否
たとえば、プロモーション中心ならPictory.AI、社内動画ならFlexClipなど、用途別に適したツールがあります。
カスタマイズの自由度が高いほど、ブランドに合わせた表現がしやすくなり、マーケティングの精度も高まります。
日本語対応や商用利用の可否
ツール選定では、日本語対応や商用利用の可否も必須です。海外製の生成AIツールには、日本語が不自然だったり、商用利用に制限があるケースもあるため注意が必要です。
チェックすべき項目は以下の通りです。
• 日本語字幕や音声合成の精度
• 商用利用ライセンスの明記
• 日本円決済や国内サポートの有無
副業や事業拡大にAIを使う場合、著作権や契約条件を見落とすと「詐欺まがい」と評判が落ちるリスクもあるため、事前確認が重要です。
特に日本市場での展開を考えるなら、日本語に強く、法的にもクリアなツールを選ぶことをおすすめします。
既存ツールとの連携や操作性の比較
使い勝手の良さも導入継続のポイントになります。特に、既存の編集ツールやワークフローと連携できるかが重要です。
以下のような点を比較して選ぶと失敗を防げます。
• Adobe PremiereやCanvaとの連携機能
• クラウド保存・共同編集が可能か
• 操作画面の日本語化やユーザーインターフェースの直感性
たとえば、動画編集に慣れていない社員が多い会社では、シンプルでドラッグ&ドロップ対応のツールが好まれます。
一方で、プロ仕様を目指す企業では、API連携や細かい調整が可能な上位ツールが選ばれる傾向にあります。
著作権や倫理面でのリスクとその対策

AIによる動画編集は便利な反面、著作権や倫理のリスクも伴います。企業で活用する以上、リスク回避のルールづくりは欠かせません。
生成物の権利関係と注意すべき点
AIで作られた動画の著作権は、使用する素材やAIの性質によって異なります。
注意すべきポイントは以下のとおりです。
• AIに与えた素材が著作権フリーか確認する
• AIツール側の利用規約に商用利用可否が記載されているか
• AIが生成した結果に第三者の権利が含まれていないか
たとえば、有名人の顔に似た合成動画を生成した場合、肖像権やパブリシティ権の問題が発生する可能性があります。
生成AIは便利ですが、結果をそのまま使うのではなく、社内で必ずチェックと承認のプロセスを設けることが大切です。
リスクを最小化する運用ルールの作成法
リスクを減らすには、社内ルールの整備が必要です。明文化されたガイドラインがあれば、現場も安心して活用できます。
おすすめのルール項目は以下のとおりです。
• 使用できるAIツールの一覧と更新管理
• 社外公開前のレビュー体制の明示
• 不適切表現・虚偽情報を含まないチェック基準
• 商用利用時の法務確認フロー
ライズ株式会社でも、AIと動画編集の研修時には、これらのルールを実際の副業参加者向けに提供し、AI導入の不安を軽減する取り組みをしています。
ルールがあることでAI活用の幅が広がり、社内外での信頼性や評判向上にもつながるでしょう。
導入効果を最大化するための社内運用の工夫

生成AIによる動画編集の効果を最大限に引き出すには、導入後の社内体制や教育、業務フローの整備が欠かせません。
ツール導入だけではなく、運用面の最適化があってこそ、コスト削減や業務効率化といった成果に直結します。
ここでは、社内で生成AIを活用するための教育と体制構築の工夫について解説します。
AIリテラシーを高めるための教育施策
AIを効果的に使うには、現場メンバーの理解が必要です。リテラシーが低いまま導入しても、ツールを使いこなせず、結果的に非効率な運用に陥るケースも見られます。
具体的には、以下のような社内教育が有効です。
• ツールの基本操作を学ぶワークショップ
• 動画編集におけるAI活用の成功事例の共有
• プロンプト(指示文)の書き方を学ぶ実践トレーニング
たとえば、ライズ株式会社でも、副業支援の一環としてAIを活用した動画編集セミナーを提供しており、参加者からの評判も高く、現場での即戦力化につながっています。
社内にナレッジを蓄積することで、導入が一時的なブームで終わらず、
持続的な成果を出し続ける基盤が整います。
試験導入から本格展開までのステップ設計
いきなり全社導入せず、スモールスタートで始めることが成功の鍵です。初期段階で小規模なチームに限定し、成果や課題を確認しながら展開範囲を広げる方法が安全です。
主なステップは以下のとおりです。
1. パイロットチームを設定し、生成AIで動画制作を試行
2. 工数・コスト・品質などの数値を比較検証
3. 社内レポートとして可視化し、関係部門へ共有
4. 業務フローやマニュアルを整備して横展開
このように段階を踏むことで、社内の反発も抑えられ、納得感を持って本格導入に進むことができます。
また、プロジェクト単位で評価指標を設定することにより、導入後のパフォーマンス分析も容易になります。
動画編集チームとマーケ部門の連携
生成AIを最大限に活用するには、編集チームとマーケ部門の連携が不可欠です。どちらか一方だけで完結させようとすると、動画の目的と成果がかみ合わなくなる恐れがあります。
理想的な連携体制のポイントは次の通りです。
• マーケチームがターゲットや配信戦略を設計
• 編集チームがAIを活用し、動画を高速生成
• 双方でレビューを重ね、コンバージョン重視の動画に仕上げる
たとえば、SNS広告用の動画であれば、マーケ側が目的を明確に定義し、編集側が適切なプロンプトを用意することで生成AIのアウトプットが目的に直結しやすくなります。
社内での縦割りをなくし、情報共有を密にすることが、生成AIの導入効果を最大化する近道になります。
プロジェクト成功の鍵は「社外発信戦略」にあり

生成AIの導入が成功したとしても、社内で留めていてはブランド価値の向上にはつながりません。
企業はその活用実績を社外へ適切に発信することで、他社との差別化や採用ブランディング、顧客への信頼獲得につながります。
発信を戦略的に行うことで、生成AIプロジェクトは社内外両面で成果を上げられます。
活用実績をコンテンツとして公開する意義
生成AIを使った動画制作の成果は、「事例コンテンツ」として社外に発信することに意味があります。
その理由は以下の通りです。
• 競合との差別化が図れる
• 企業の技術力・先進性をアピールできる
• 採用活動での信頼獲得につながる
たとえば、制作した動画をYouTubeに公開し、概要欄で生成AIツールの活用背景を紹介するだけでも、視聴者に対して透明性の高い取り組みとして好印象を与えられます。
ライズ株式会社でも、福井亮眞の名義で実績をオウンドメディアに掲載し、副業・動画編集・AI分野での信頼性向上に活用しています。
自社の強みを「見える化」することで、マーケティング効果も高まります。
メディアやSNSを通じたブランド価値向上
自社だけでなく、外部のメディアやSNSを活用することで、生成AIの取り組みをさらに広く知ってもらうことができます。
たとえば以下の方法があります。
• 導入事例をプレスリリースとして配信
• LinkedInやX(旧Twitter)での活用ストーリー発信
• 業界紙や専門メディアでのインタビュー掲載
こうした発信により、リード獲得だけでなく、「信頼性の高い企業」としての評判づくりにも効果があります。
また、社外発信の積み重ねは、生成AIを活用する企業文化の醸成にもつながるため、内外にとってポジティブな効果をもたらします。
発信しなければ、成果がないのと同じと捉え、積極的に情報を届ける意識を持つことが重要です。
まとめ|動画編集に生成AIを活用して企業価値を高めよう
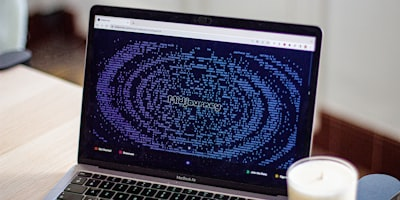
生成AIを活用することで、動画編集の時間とコストが大きく下がります。
実際に多くの企業が導入し、プロモーションや社内広報で成果を出しています。
活用には、目的に合ったツール選定と、社内体制の整備が重要です。さらに、実績を外部に発信することで、企業の信頼性やブランド力も高まります。
まだ導入していない方は、事例を参考に一歩踏み出してみてください。小さな一歩が、組織全体の生産性向上と競争力強化につながります。
ライズ株式会社代表取締役社長福井亮眞です。2016年に代理店営業を開始。スクール詐欺、投資詐欺、コンサル詐欺にことごとく騙され借金600万円を背負う。「動画編集」「Tiktok」「SNS運用」をきっかけに軌道に乗り、2019年10月に法人化。現在は「SNS運用代行業」「営業代行業」「代理店事業」「独立支援」を行い、企業様と関わりを深めながら、自社の「コンテンツ制作」も行なっている。
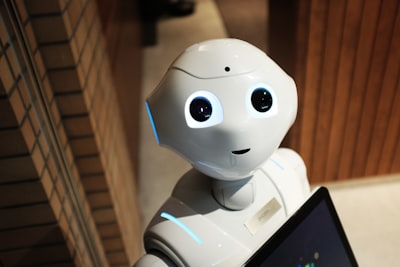

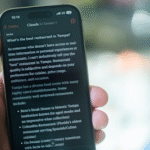
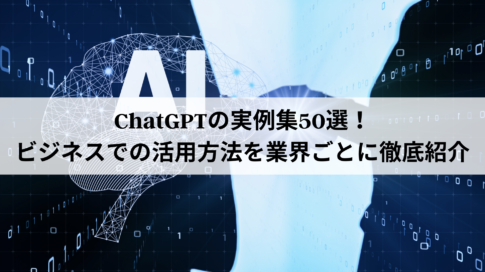

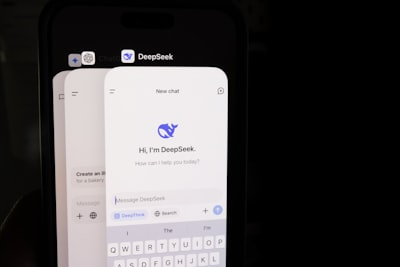

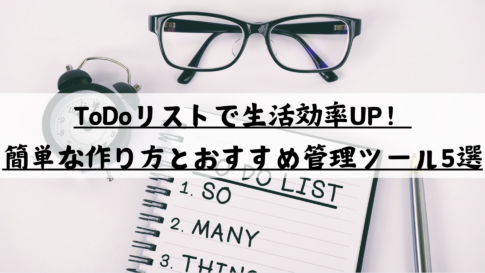





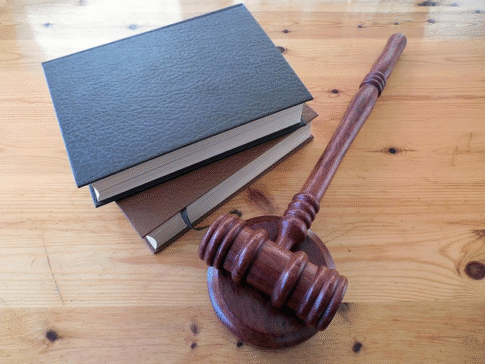


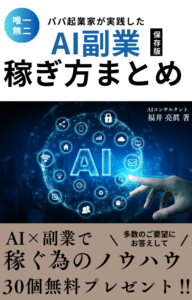

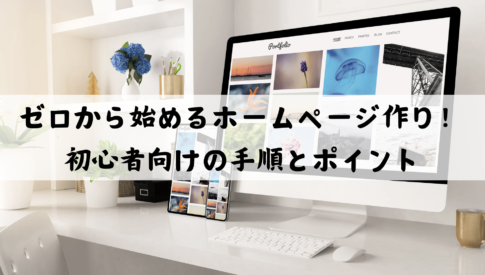
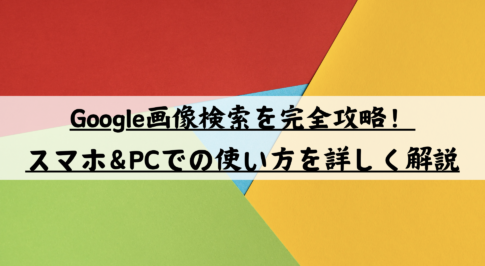
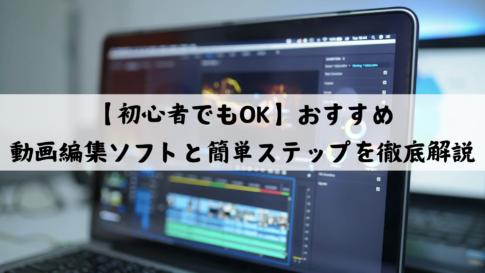

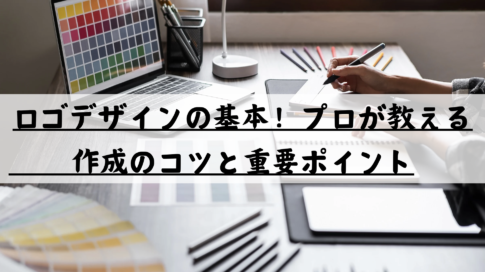
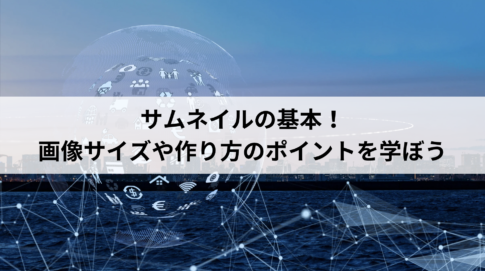

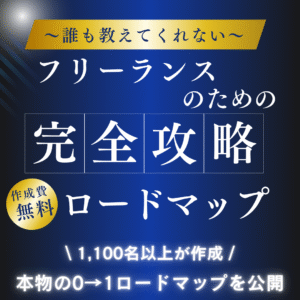
コメントを残す