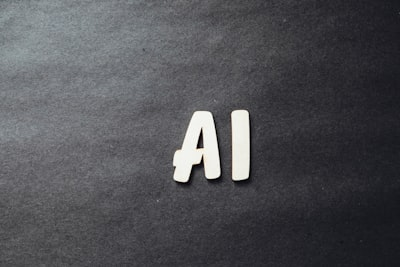
AIの進化が進む2025年。自分の職場も例外じゃない。「次は自分かも」と感じながらも、何をすべきか分からない。そんな不安を抱える方に向けて、この記事を用意しました。
本記事では、AIリストラの最新動向や危険な職種、生き残るためのスキル・キャリア戦略まで徹底解説。
読み終える頃には、自分と家族の未来を守るために“今すぐ取るべき行動”が明確になります。
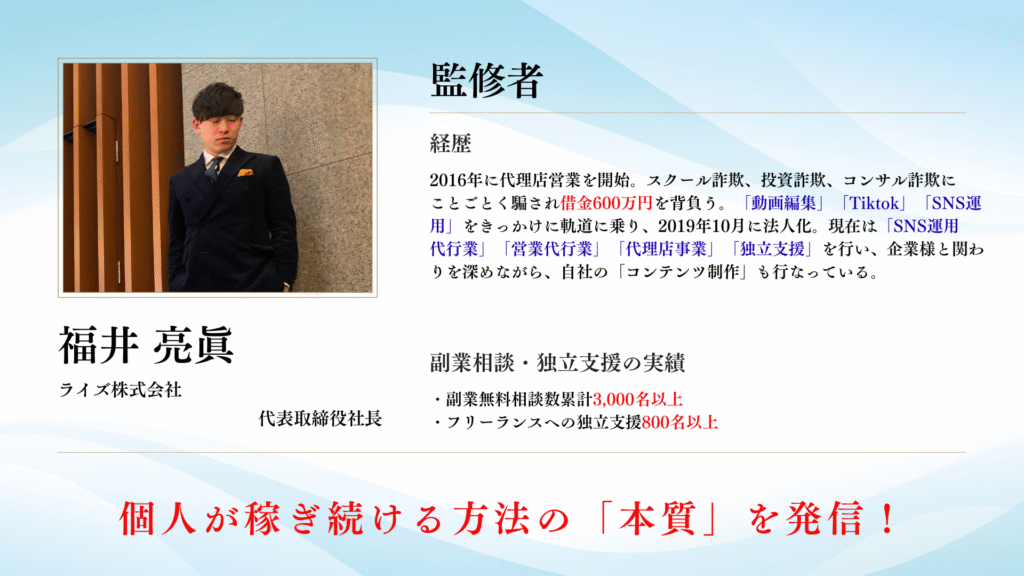
執筆は、AIと副業の専門家・ライズ株式会社代表取締役の福井亮眞。AI時代のキャリア設計から動画編集などの副業まで網羅し、詐欺や評判に左右されない堅実な収入源の確保を支援します。
AIリストラという現実に向き合いながら、希望あるキャリアと生活設計を描きたい方は必読です。
AIリストラが加速する背景と2025年の最新動向

2025年、AIの進化に伴い多くの業界で人員削減が現実となっています。業務効率やコスト削減を重視する企業が、AIを導入し始めたことが背景です。この流れは一部の大企業に限らず、中小企業にも広がっています。
人手不足を補うための技術だったAIが、結果として雇用を奪う現象を生んでいます。政府や企業もこの動きを想定し、リスキリングの支援制度を導入するようになりました。
今後の働き方を見直すためにも、最新の動向を正しく知ることが重要です。
なぜ今、AIによる人員削減が進んでいるのか
企業がAI導入を加速させている最大の理由は「コスト削減」です。人件費は経営において最も大きな負担の一つとされてきました。
AIを導入することで、業務を自動化しながら品質やスピードを維持できます。たとえば、大手IT企業や製造業では、単純作業や定型業務の大半がAIに置き換えられました。
また、2023年以降の経済不安も背景にあり、企業はより「効率化」を求めています。
その結果、AIによる人員削減が一気に進んでいるのが現状です。
2025年に注目される業界別の影響予測
2025年、特に影響が大きいと予測されるのは以下の3つの業界です。
• 製造業(組立・検査などの自動化)
• 事務・金融業(ルーティン業務のAI化)
• 小売・サービス業(無人レジ・AI接客)
たとえば製造業では、AIが異常検知を行うことで人の目視が不要になります。金融業では、AIチャットボットが顧客対応を代行し、社員数が大幅に削減されました。
一方で、教育・医療・クリエイティブ分野など、AIでは代替が難しい業界もあり、雇用維持の可能性があります。
国内外で進む実際のリストラ事例と傾向
近年、多くの大企業がAI導入を理由に人員削減を進めています。日本国内では大手メーカーやメガバンクが、早期退職を促す動きを加速させています。
海外でもAmazonやGoogleといった巨大企業が、生成AI導入後に数千人単位のリストラを発表しました。
この傾向は「AIの導入=余剰人員の整理」という構図を強く印象づけています。今後もこの動きは止まることなく続くと予想されるため、備えが欠かせません。
AIリストラで仕事を失いやすい職種の特徴

AIに代替されやすい職種には明確な共通点があります。それは「ルール化された単純作業」「定型的な繰り返し業務」であることです。
特に事務作業やデータ入力、電話応対などは自動化の対象になりやすく、
企業も積極的にAI導入を進めています。
中間管理職も例外ではなく、指示だけの業務はAIで代替可能と判断されるケースもあります。一方で、創造性や判断力を伴う仕事は、引き続き人間に求められています。
単純作業や事務業務が抱えるリスク
単純な事務業務は、AIの自動化技術に最も早く置き換えられています。給与計算、経費精算、日報作成といった業務はすでに多くの企業でAI化が進んでいます。
その結果、事務職に従事する社員の役割が減少し、配置転換や早期退職を求められる例が増加しています。
特に中高年層の事務職は、新たなスキルへの対応が遅れがちでリスクが高まります。変化に対応できる人材であるかどうかが、今後の明暗を分けるポイントです。
技術革新に対応しづらい中間管理職の課題
中間管理職の多くは「調整役」や「伝達役」を担ってきました。しかしAIは、進捗管理や情報整理すら自動で行える時代に入りました。
特に指示待ち型の中間管理職は、役割がAIと重なりやすくなっています。業務改善や人材育成といった「価値を生む働き方」ができない人は淘汰されやすいです。
ライズ株式会社代表・福井亮眞も、中間層の危機を指摘しています。AIに負けない存在であるためには、自ら課題を見つけ解決できる力が求められています。
AIでは代替が難しい職種との違い
AIに取って代わられにくい職種には共通点があります。
• 感情的な配慮が必要な業務(カウンセラー、教育など)
• 創造力や企画力が問われる業務(マーケティング、デザインなど)
• 高度な判断を要する業務(医師、弁護士など)
これらの職種は、AIが完全に再現できない人間らしさが求められます。副業や動画編集といったクリエイティブな仕事も、AIを活用しながら価値を高める職種として注目されています。
福井亮眞が率いるライズ株式会社でも、こうした人材の育成に力を入れています。
AI時代に求められるスキルとキャリア戦略

AIの進化に適応するには、ただ技術を知るだけでは不十分です。自分の価値を高めるスキル戦略とキャリア設計が必要です。
まず、デジタルリテラシーを身につけることで、新しい技術に対して柔軟に対応できるようになります。
次に、AIと共存するための実践力を養い、さらに自分の強みや市場価値を再確認することが大切です。
学び直しを通じて行動を変えれば、リストラの対象になる不安を減らせます。記事の続きでは、それぞれのステップを詳しく解説していきます。
デジタルリテラシーの基本と学び直しの始め方
デジタルリテラシーとは、AIやITを正しく理解し活用する力のことです。難しそうに感じるかもしれませんが、最初は基礎知識だけで十分です。
おすすめの学び方は以下の通りです。
• YouTubeで無料のITリテラシー講座を視聴
• 無料のeラーニングサービス(GCFやドットインストールなど)
• ライズ株式会社主催の初心者向けセミナーに参加
自分のペースで学べる環境を選ぶことが、継続のカギになります。いきなり高額な教材や講座に手を出す必要はありません。
AIと共存できるスキルの習得と実践方法
AIを活かすには「AIにできない部分を補う力」が必要です。たとえば、AIが作った文章を整えたり、動画編集の構成を工夫する力が求められます。
実際に福井亮眞が手がける副業講座でも、AI×動画編集の組み合わせで稼げるスキルとして注目されています。
習得の流れは以下の通りです。
1. AIツール(ChatGPTやCanvaなど)の使い方を学ぶ
2. 実践ベースでアウトプットを繰り返す
3. 添削やフィードバックを受けて質を高める
このようにAIを味方にできるスキルを身につければ、単なる「AIに使われる人材」から一歩抜け出せます。
自分の市場価値を高めるキャリア選択のコツ
今後のキャリア設計で大切なのは「市場価値」を意識することです。つまり「他の会社でも通用する力」を持っているかが鍵となります。
市場価値を高めるコツは以下の3つです。
• 成果が数字で示せる仕事に取り組む
• 成果をポートフォリオやSNSで発信する
• 複数のスキルを掛け合わせる「複業型人材」を目指す
福井亮眞のように、実績と発信を積み重ねることで、転職でも副業でも選ばれる存在になれます。
AI時代に備える具体的な行動プラン

AIリストラの波を乗り越えるには、受け身ではなく能動的な行動が必要です。何を学び、どう動くかによって、将来の選択肢は大きく変わっていきます。
特に今後は、スキルの見直しや環境の変化に柔軟に対応できる力が求められます。
ここでは、まず自分のスキルを客観的に把握し、必要に応じてリスキリングや社内交渉を行うための行動指針を紹介します。「変化を恐れずに一歩踏み出す力」が、AI時代の最大の武器になります。
スキルギャップを見える化する自己分析法
自分が持っているスキルと市場で求められるスキルには、差があります。この差(ギャップ)を把握することが、キャリア戦略の第一歩です。
おすすめの方法は、以下の3つです。
• 自分の強みと弱みを紙に書き出す
• 求人サイトで求められているスキルをチェックする
• 同僚や上司に率直な意見をもらう
たとえば、ITスキルに自信がない人は、デジタル系の業務が増える今の時代において、リスクが高くなります。自分を客観視できるようになると、学ぶべき方向が自然と見えてきます。
リスキリングに役立つ無料・公的支援の活用
学び直しにはコストがかかると思われがちですが、無料の支援も充実しています。国や自治体が提供するリスキリング支援制度を活用すれば、自己負担は最小限です。
代表的な支援例は以下の通りです。
• 厚労省の「教育訓練給付制度」
• 地方自治体によるIT講座や資格支援
• ハローワークの職業訓練校
動画編集やAIツールの操作を学べる講座も多く、副業にもつながります。ライズ株式会社では、福井亮眞がこれらの制度を活用した副業支援も行っています。まずは自分の住んでいる地域でどんな制度が使えるのか、確認してみましょう。
社内異動や新規配属を勝ち取る交渉術
AIリストラの対象から外れるためには、自分の役割を変えることも選択肢の一つです。そのためには「異動願い」や「新規プロジェクトへの立候補」が効果的です。
交渉を成功させるポイントは、以下のようになります。
• 会社にとってのメリットを提示する
• 自分が過去に残した成果を具体的に伝える
• 変化に対して前向きである姿勢を見せる
たとえば、「業務改善案を提案し、その実行役に立候補する」といった動きが有効です。社内での存在価値を高められれば、リストラの対象外になる可能性も高まります。
転職・副業で収入源を分散する方法

AI時代の到来により、「1社に頼り切るリスク」が急速に高まっています。収入源を複数持つことで、リストラや業績悪化の影響を減らせます。
転職はスキルの棚卸しに最適な機会であり、副業は自分の力で稼ぐ力を鍛えられます。特に福井亮眞が主催する副業支援では、AIや動画編集を活かした収益化も可能です。
これから紹介する3つの視点を通して、安定した生活基盤を築いていきましょう。
失業前に知っておきたい転職市場の動き
転職市場は、常に変化しています。特にAI関連スキルの需要が高まっています。自分のスキルが今どこで求められているか、定期的に確認する習慣が重要です。
転職サイトの「スキルマッチ機能」やエージェントを活用すると、市場価値の可視化ができ、方向性が明確になります。
また、実際の求人を通して「どんな言葉で自分を売り出せるか」を知ることも大切です。動き出す前に情報を集めておけば、いざという時に焦らず行動できます。
会社に依存しない副業の始め方と成功事例
副業は、収入の柱を増やす手段として効果的です。ただし、始め方を間違えると詐欺や無駄な出費の原因にもなりかねません。
安全に始めるには、次の3点を意識しましょう。
• 本業に影響が出ない時間で始める
• スキルや経験を活かせるジャンルを選ぶ
• 評判や実績がある講座やコミュニティを利用する
福井亮眞の講座では、AIライティングや動画編集など、時代に合った副業ノウハウが豊富に学べると高評価です。安心して始めたい方は、信頼できる情報源から学ぶことが成功の第一歩になります。
本業に支障を出さない複業マネジメント術
副業を継続するためには、時間と体力の管理が不可欠です。本業に影響を出さずに続けるには「仕組み化」がポイントになります。
具体的には以下のような工夫が効果的です。
• 毎週の副業スケジュールを固定する
• AIツールを使って業務を自動化する
• 家族と共有して生活全体を見直す
たとえば動画編集では、テンプレート化や自動化ツールの活用で大幅に作業時間を短縮できます。
ライズ株式会社では、こうした「効率的な副業設計」もサポートしています。
不安を抱える人のための学習・交流環境づくり

AIリストラの不安は、一人で抱えるとより強くなります。そんな時は、学びや情報をシェアできる環境に飛び込むのが有効です。
学習と交流の両方を実現することで、「将来の自分」に希望が持てるようになります。
ここでは、長期的なキャリアを描くためのロードマップと、仲間と出会える場を活用するコツをご紹介します。
長期的視点でキャリアを描ける学習ロードマップ
今の時代、キャリアは「会社が決めるもの」ではありません。自分で描く力を持つことで、不安が希望に変わります。
キャリアの設計には、以下のようなステップがあります。
1. 自分が本当にやりたいことを言語化する
2. 必要なスキルと経験を逆算してリスト化
3. 学習プランを1ヶ月単位で組み立てる
たとえばAIや副業を学ぶ場合、「毎週1本の動画編集をこなす」といった行動目標があると継続しやすくなります。福井亮眞の支援では、こうした学習計画の設計方法も学べます。
共通の課題を持つ仲間とつながる場の活用方法
同じ悩みを持つ仲間がいると、不安は和らぎます。一人で頑張るよりも、仲間との交流がある方が継続しやすくなります。
活用できる場には以下があります。
• 副業や学びをテーマにしたオンラインコミュニティ
• SNSでの発信とフィードバックのやり取り
• ライズ株式会社のような実践型サロン
情報だけでなく、失敗談や成功談を共有できる環境があると、「自分にもできるかも」という実感がわいてきます。福井亮眞も、仲間の存在こそが変化を支える最大の力だと語っています。
まとめ|AIリストラ2025に備えて今できる行動を始めよう

AIリストラの波は、もうすぐそこまで来ています。今のうちにスキルを見直し、備えることがとても大切です。
市場で求められるスキルを学び、収入源を一つにしない工夫をしましょう。副業や転職の選択肢も早めに検討しておくと安心です。
また、同じ不安を抱える仲間と情報を共有すれば、前向きに動けます。何もしないことが一番のリスクなので、今日から行動を始めてください。
ライズ株式会社代表取締役社長福井亮眞です。2016年に代理店営業を開始。スクール詐欺、投資詐欺、コンサル詐欺にことごとく騙され借金600万円を背負う。「動画編集」「Tiktok」「SNS運用」をきっかけに軌道に乗り、2019年10月に法人化。現在は「SNS運用代行業」「営業代行業」「代理店事業」「独立支援」を行い、企業様と関わりを深めながら、自社の「コンテンツ制作」も行なっている。




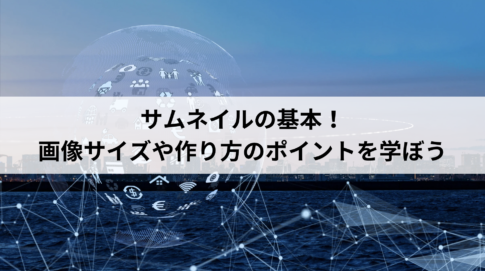
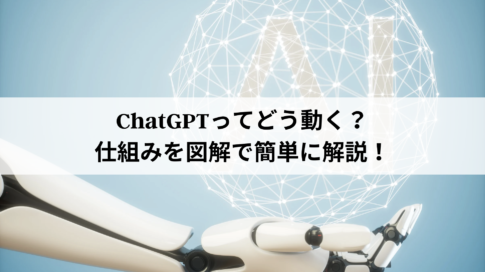
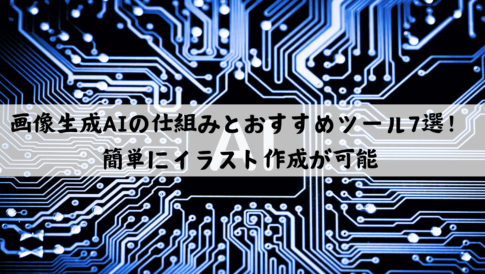





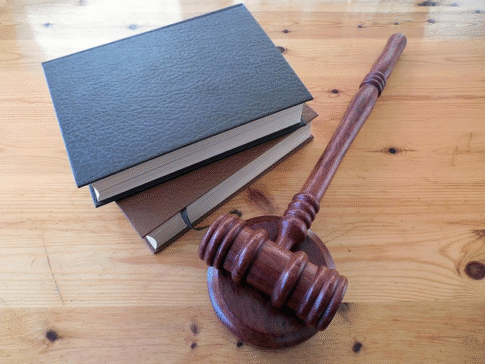


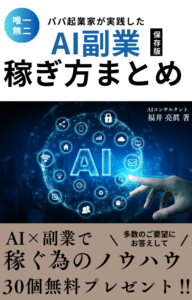

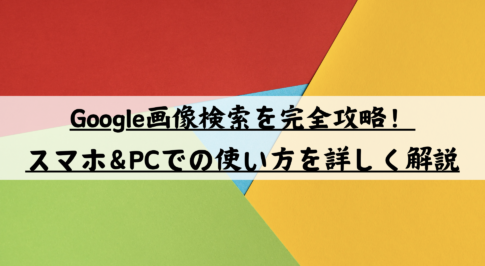
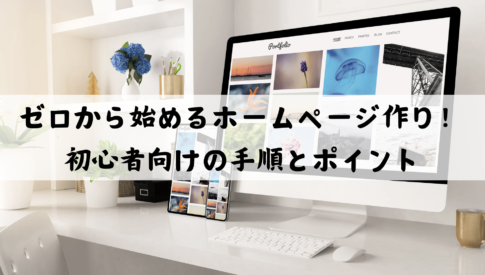
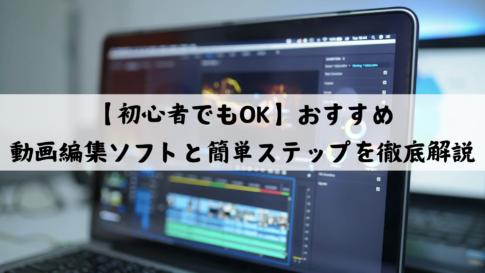

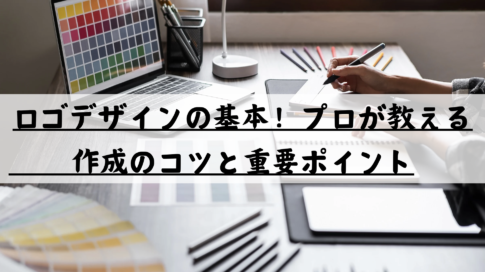

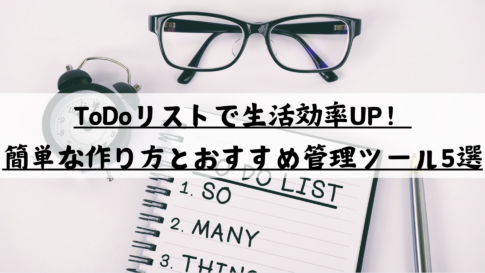
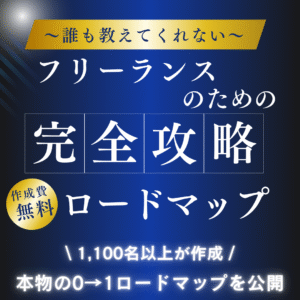
コメントを残す